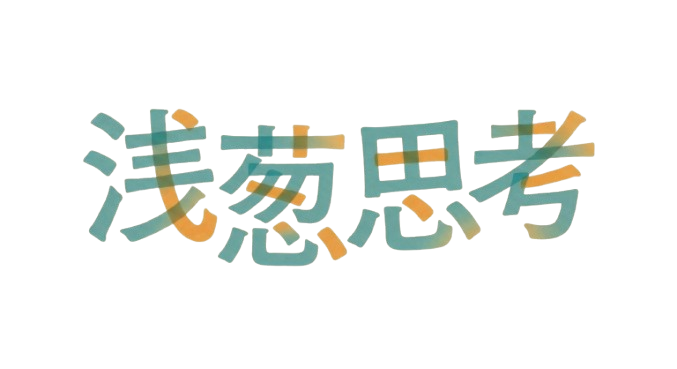AIとの出会い、仕事の変化
私がAIツールを使い始めたのは、ChatGPTが最初にリリースされた頃。
最初の課金は、2023年03月でした。(笑)

当初は文章作成や単純な質問への回答など、基本的な用途に限定して使用していました。
最初の頃はAIのできることも限られていましたし、「頑張って使う」のフェーズだったと思います。
しかし、GoogleやAnthropicなどの競合サービスが登場し、急速に業界が盛り上がって進化していく中で、AnthropicのClaude 3.5 sonnetの文章生成能力の高さに気づいたことが、私のAI活用の転機となりました。

現在では、エンジニアではない私でもAIの助けを借りてコードを書いたり、プレゼンテーション用のグラフを作成したり、データ分析をしたりできるようになりました。
正直、私はAIにどっぷりハマってしまって、仕事もまったくもって別のものになりました。
「なぜ私はAIを使いこなせるのか」という問い
AIツールを使い続ける中で、ふと気になる現象に気づきました。
同じAIツールを使っても、人によって得られる結果に差がある。
最近は、企業でAI活用のサポートをしたり、自社内でもセミナーのやりとりをしていると、「この人はすごく時間がかかりそう。」「この人はおそらくこれ以降は自力でできるだろう」と感覚的に思うこともあります。
私はテクノロジーの進化によって、ユーザースキルの差は勝手に埋まっていくと思っていたのです。AIの性能が上がったので、誰でも同じように使えば同じ結果が得られるだろう。と。
しかしAIを活用できる人とそうではない人の格差はAIの性能が上がっても広くなっていっているように感じます。
「メタ認知」との出会い
なぜAIを使いこなせる人と、そうではない人がいるのか?
Claudeとの対話の中で「メタ認知」という概念を知ったとき、大きな気づきがありました。

私は、メタ認知という言葉を初めて知りました。
メタ認知は「自分の思考プロセスについて考える能力」のこと…と、ChatGPTに教わりました。(笑)
自分がどのように考え、判断し、学んでいるかを理解し、評価する能力。
私がAIを効果的に活用できている理由が、このメタ認知能力と深く関連していることをClaudeから教わりました。
これは仕事の自信すら無くしていた私にとって、大きな発見で、希望にもなりました。
自分の理屈っぽさ…それを受け入れる
私はAIが出てくる前から、すごく理屈っぽい人間でした。何事にも理由や根拠が必要でした。
「なんでやるのか?」
「何を解決したいのか?」
「なぜそうしたいのか?」
「なぜ数ある中からその手段なのか?」
「問題の根本は何なのか?」
1つの事柄でも、原因から考え始めて、隅々まで考えを巡らせることは私の習慣だったのです。
私の性格を言い表すときに「理屈っぽい」が選択肢に出てくるくらいには、私の中でこの考え方が浸透していて、プライベートでは意識的に抑制していたほど。
いちいち「理由は?」とか聞かれたら、煩わしいですもん。(笑)
この理屈っぽいともいえる「目的思考」が、AIとの対話においても自然と活かされていたようです。

例えば、AIの使い方で以下のような例があります。
- AIに質問する前に、目的やビジョンを設定する
- 回答が不十分な場合、なぜそうなったのかを振り返る
- 繰り返し、うまくいかないとき、これまでの対話を分析して傾向を変えてみる
- より良い結果を得るために、聞き方や渡すデータを変えてみる
これらを頭の中で無意識に繰り返してきたので、AIを使う際にもこの思考プロセスが難なくできる。それが、AIからより質の高い回答を引き出すことにつながっていたのです。
技術やテクニック以外にも、「思考法」がカギだった

この自分の思考プロセスに関する気づきは、仕事の自信を無くしていた私の励みになりました。
そもそも落ち込んでいなかったら、「AIを使えてすごいって言われるけど、AIがすごいだけだよね?(シクシク)」なんて、泣き言は出てこないですからね。(笑)
AIを効果的に活用するには、技術的なスキルより「思考法」と「好奇心」の方が重要かもしれません。
メタ認知以外にも、この辺は使いこなせている理由かなーと思う泥臭いスキルもありますが、それは別の時にぺらぺら書いてみます。